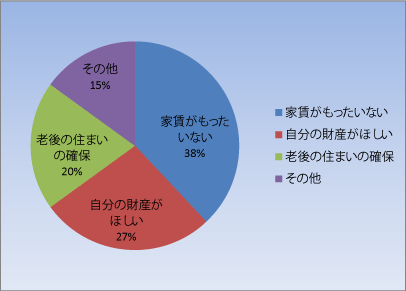■コスト積算による分譲の仮価格と“相場”の比較。
不動産の取引価格は、近隣物件の取引事例を参考にして決められます。
いわゆる“相場”と呼ばれるものです。
新築分譲マンションも基本は同じです。
周辺の物件相場と“コスト積算による分譲の仮価格”を見比べて分譲価格を思案します。
比較の際に用いられるのが“坪単価”です。
単に3LDKと言っても、物件により住戸の広さはまちまちです。
それで、坪あたりの単価に換算して比較をします。
通常は、過去の“相場”を基にすれば大方の分譲価格の目安が立ちます。
しかしながら、土地価格や建設費の高騰などといった“経済情勢”が変化すると、
分譲価格の設定が難しくなります。
この場合、大きく分けて3つの方法が考えられます。
・分譲坪単価が上がるのを覚悟の上で、仕様や設備の質を落とさずにプランする。
・過去の“相場”に近づけるために、仕様や設備のランクを下げてプランする。
・住戸の広さを減らして(=戸あたりの坪数を狭くする)、
坪単価ではなく“値頃”を従来の“相場”に近づける。
■VE(バリュー・エンジニアリング)
仕様や設備の魅力を維持しながら、分譲坪単価を下げる。
そんな都合のいい方法は無いのでしょうか?
いいえ、それがあるのです。
ここで登場するのがVE(バリュー・エンジニアリング)という手法です。
VEとは、製品やサービスの果たすべき「機能」を
ユーザーの立場からとらえて分析し、
顧客が求める機能を、
最低のライフサイクル・コストで達成する手段を実現する手法です。
平たく言えば、コストパフォーマンスを重視する手法です。
システムキッチンやバスユニットなどの設備を例に説明しましょう。
これらの設備は、設備の専門メーカーから調達するのですが、
同様の機能を備えていてもメーカーによって価格が異なります。
トップメーカーの設備機器は往々にして高額です。
同等の仕様を提供する他の設備メーカーの製品を導入することで、
設備の魅力を損なうことなく、コストを下げることが可能です。
また、必要性の低い仕様は省いたり変更したりした、
オリジナル仕様の設備を設備メーカーに発注して、
コストを下げても機能性は損なわない設備を提供することも可能です。
このような考え方で、すべての設計仕様を再チェックするのがVEです。
しかしながら、VEを尽くしても、坪単価の軽減には限度があります。
最終的には、消費者の反応を見ながら分譲価格を調整する方法があります。
以降は「最終章」に続きます。