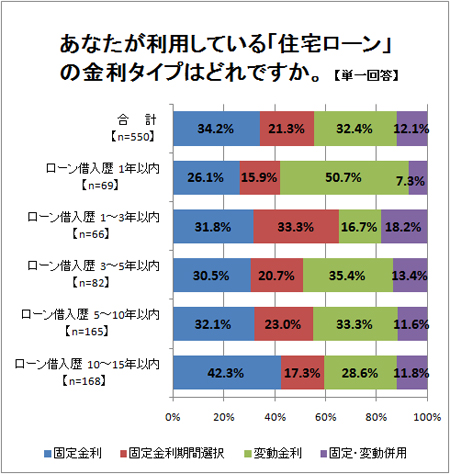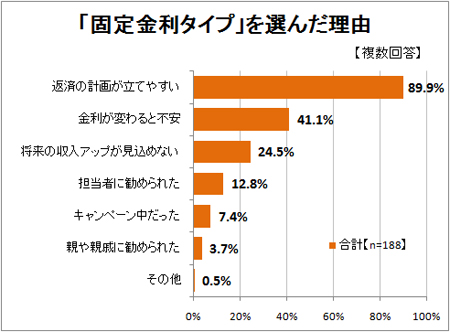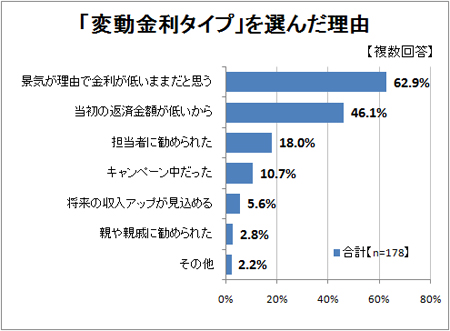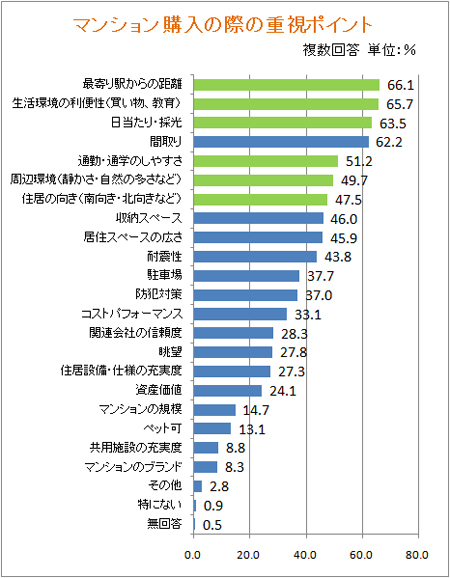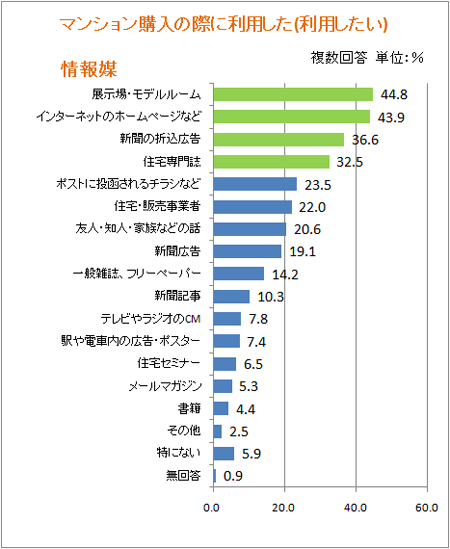“分譲マンションの価格はこうして決まる”の章で、価格の成り立ちを説明いたしました。当然ながら、そのコストの中には“値引予算”などというものはアリマセン。
では、なぜ、値引きが行われる物件があるのか?
■分譲マンションには“鮮度”がある。
分譲マンションの販売は、“当初3ヶ月が勝負”と言われています。
分譲を開始しして3ヶ月の販売進捗を見れば、
その物件の販売スピードの“およそ”が推測できます。
周辺に競合物件が発売されれば、
自ずと、先に発売したマンションのニュース性は落ちます。
ましてや、後発で発売された物件が、立地、仕様、価格などの魅力が勝っていれば、先発の発売物件の販売スピードはさらに減速します。
元々、競合が多いエリアに物件を投入した場合は、更に顕著です。
魅力が劣る物件の販売スピードは激減し、まさに“商品としての鮮度”が落ちます。
また、競合物件が出てこなくても、販売期間が長きにわたると、
“商品としての鮮度”が落ちます。
■販売期間が延びれば経費がかさむ。
販売期間が予定よりも延びれば、販売にかかる経費がかさみます。
人件費や広告宣伝費などが目論見よりも多くかかることになります。
販売期間が延びるのに要する“経費”を先取りして、
販売のスピードアップを図るために行われるのが“値引き”です。
当然ながら、“値引”は当初に予定していた利益の減少になります。
度を超すと、事業そのものが赤字になってしまいます。
■値引きを行う物件と行わない物件。
値引きに対するスタンスは、ディベロッパーにより様々ですし、
同じディベロッパーでも物件毎に異なります。
値引き対応をしないディベロッパーや物件もありますし、
激戦区では、発売初期から値引きを行う物件も見うけます。
* しかしながら、資金体力が弱いディベロッパーが市場から退場した今、
* 値引き対応をする物件には限りがあります。
値引きが期待できるかどうかの目安は、
竣工(物件の完成)からどれだけの期間を経過しているかによります。
■価格交渉は販売員を味方につけろ!
販売会社の営業マンからよく聞く話です。
物件のご説明を始めたら、
いきなり価格交渉をなさるお客様がいるそうです。
十分な説明を聞かない前に、
いきなり「オタクはいくら値引きしてくれますか?」では、
販売員に与える心象が良くありません。
販売員も人間です。自社の商品へのプライドもありますし、
他社と比較して自社の商品の魅力がどうかと言うことも承知しています。
一生一大の買い物です。
時間を掛けて販売員とコミュニケーションを取るのが得策です。
販売員の一存で決定できる値引きの枠には限りがあります。
上司の決裁を仰がないと値引きできない場合も少なくありません。
そのためにも、販売員を味方につけるような商談が大切でしょう。